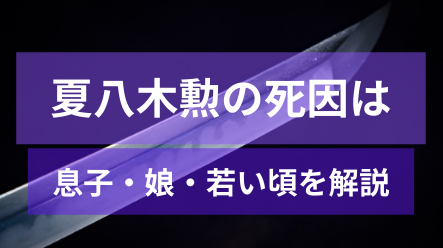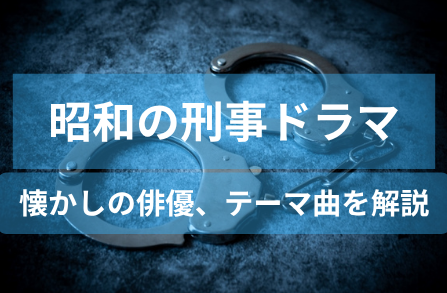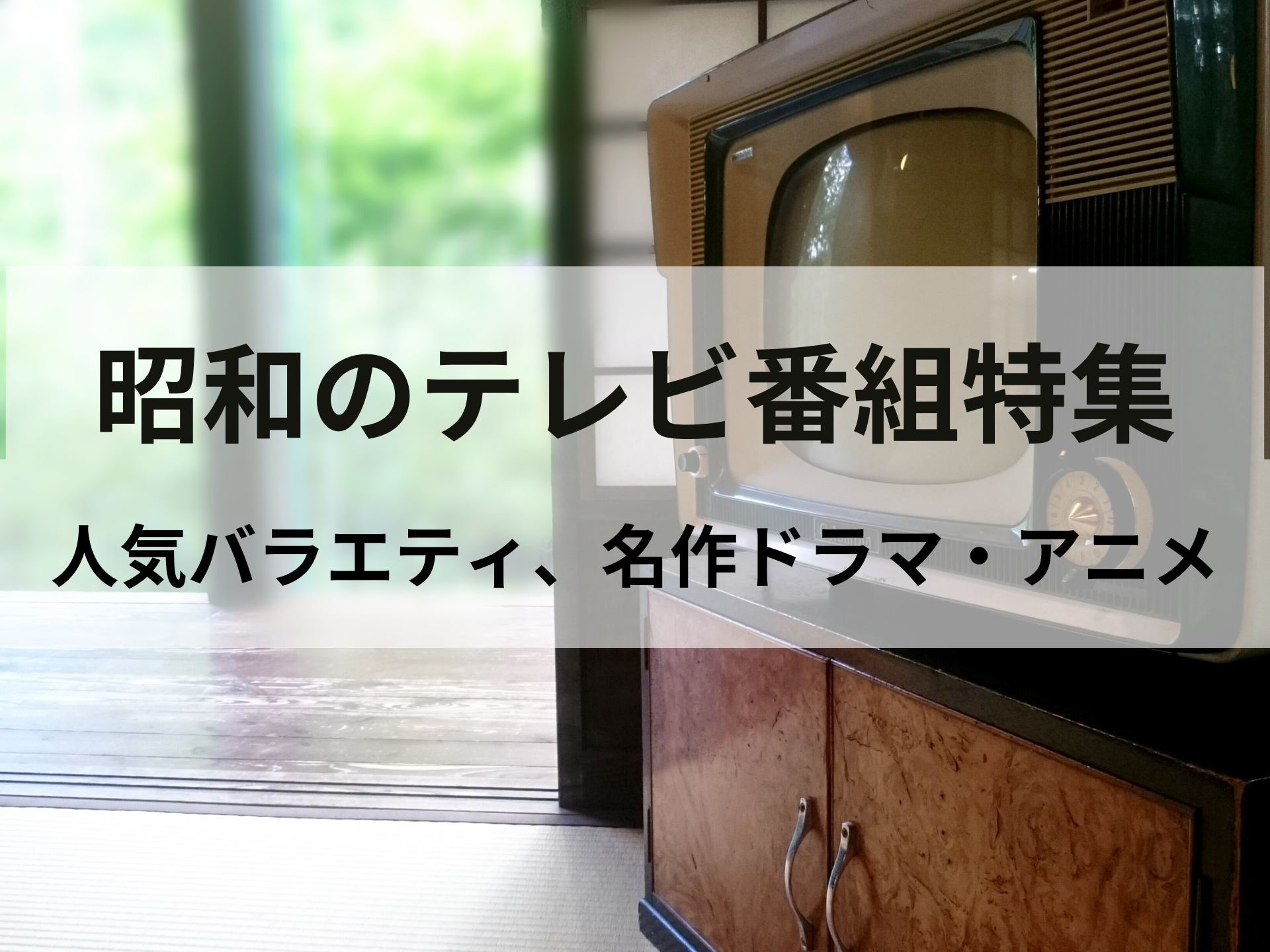大川橋蔵の死因は?「銭形平次」が有名、息子は俳優?妻、家系、家族を解説

昭和といえば時代劇に人気が集まっていた時代です。
その時代劇のスターとして、今も輝かしい存在のひとりに、二代目大川橋蔵さんがいらっしゃいます。
この記事では、二代目大川橋蔵の死因を中心に、大川橋蔵さんの謎に迫っていきます。
なお、ここでは二代目大川橋蔵さんを「大川橋蔵」として述べさせていただきます。
もくじ
大川橋蔵(二代目)とは?
ここでは大川橋蔵さんの経歴や芸能界での大まかな活躍を解説していきます。
大川橋蔵の経歴
大川橋蔵さん🥺🙏 https://t.co/dkvd2CRKBx
— カウンター(即興ソロダンス) (@yGMcpNEi5EXnHR6) December 7, 2024
大川橋蔵さん(本名:丹羽 富成(にわ とみなり))は、1929年4月9日、東京の柳橋で誕生しました。
母は花柳界出身の笠原たか、父は人形町でガラス問屋を営んでいた田中進という、芸能とビジネスの両面を持つ家庭環境で育ちました。
そして、橋蔵さんは、幼くして母方の祖母(小野家)に引き取られ、小野富成として育ちました。
母方の祖母は柳橋の名妓として知られ、その夫である小野六三郎は市川瀧之丞の名で歌舞伎役者として活躍していたという、芸能界の血が流れる家系に育ち、幼い頃から舞踏を仕込まれました。
わずか6歳の1935年、市川男女丸の名で歌舞伎座「先代萩」の鶴千代役を演じ、華々しい初舞台を飾ります。
学歴は、日本大学第三高等学校を卒業しました。
その後、六代目尾上菊五郎の妻の養子となり、1944年には、二代目大川橋蔵を襲名します。
六代目菊五郎が亡くなった後は、菊五郎劇団に所属して、特に立女形(たておやま)として頭角を現し、七代目尾上梅幸や七代目中村福助に並ぶ存在として期待を集めたのです。
若手歌舞伎役者として着実にキャリアを積み重ねる中で、特に舞踊の分野での評価が高く、六代目菊五郎から受け継いだ繊細な所作と表現力は、多くの観客を魅了しました。
歌舞伎界での活躍は目覚ましく、特に女形としての将来性を高く評価されていた時期でした。
しかし、その後の人生は思わぬ展開を見せることになります。
映画界からの熱心なオファーを受け、苦悩の末に新たな道を選択することになったのです。
この決断は、日本の芸能界に大きな影響を与えることになりました。
歌舞伎役者から映画俳優の道へ
昭和30年(1955年)、歌舞伎界の若手女形として将来を嘱望された大川橋蔵さんでしたが、六代目尾上菊五郎さんが亡くなった後、強力な後ろ盾をなくし、歌舞伎界での将来に不安を抱くようになります。
すでに映画俳優としてデビューしていた、八代目市川雷蔵の強い勧めもあり、迷った末に、菊五郎劇団に在籍しながら東映へと転身を果たします。
1955年、デビュー作品「笛吹若武者」では美空ひばりや大友柳太郎と共演し、その甘いマスクと品格ある若侍ぶりで一躍スターの座に上り詰めました。
翌年には「若さま侍捕物帖」で早くも主演を務め、1959年の「新吾十番勝負」シリーズでは東映の看板スターとして不動の地位を確立しています。
歌舞伎で培った所作の美しさと足腰の強さを活かした立ち回りは、時代劇映画の黄金期を支えた重要な要素となりました。
特筆すべきは、映画と並行して「東映歌舞伎」での舞台活動も継続し、市川右太衛門との共演で浮舟太夫を演じるなど、女形としての実力も遺憾なく発揮したことです。
その後、テレビ時代劇「銭形平次」でも18年という長期にわたって主演を務め、ギネスブックに「テレビの1時間番組世界最長出演」として認定される偉業を成し遂げました。
大衆娯楽としての時代劇の魅力を存分に引き出した橋蔵さんの演技は、多くの視聴者を魅了し続けたのです。
大川橋蔵、歌舞伎役者・俳優。
— 日大三高(非公式) (@akasaka_machida) May 25, 2024
旧制日大三中に学ぶ。
歌舞伎役者から俳優に転身。
銭形平次は大人気で18年続き、「1人の俳優が同じ主人公を演じた1時間ドラマ」世界最長としてギネスブックに認定された。
平次出演優先のため、大河ドラマ主役を辞退している。#日大三の人々#日大三052#大川橋蔵 pic.twitter.com/SSMuQiSKek
大川橋蔵の死因は?
大川橋蔵さんの死因について、様々な憶測が飛び交っていますが、その真相を解明していきます。
大川橋蔵の死因は「結腸がん」
大川橋蔵さんは、1984年12月7日午前1時29分に亡くなりました。
死因は「結腸がん」であり、その後肝臓への転移も確認されました。
直接の死因は、がんが肝臓に転移して、その結果「急性肝不全」を発症して亡くなりました。
「結腸がん」であることは、ご本人には告知されていませんでしたが、橋蔵さんは、「俺は自分の病気は知ってるよ」と言っており、自分の病気のことを気づいていたそうです。
昭和の当時は、「がん」は不治の病であり、本人にがんの告知をすることは稀でした。
私は平成の初期に病院の職員として働いていましたが、その頃、同じ病院の医師が、患者さんに「がん」であることを告知したことを巡って、職員の間で、告知の是非を問う大討論が起きて、大騒ぎになったことがあります。
現代では、「がん」は治る病気として認識され、告知することが当たり前になってきていますが、大川橋蔵さんががんに罹った昭和の頃は、告知することは滅多になく、本人には隠すのが一般的でした。
ですから、橋蔵さんもご家族も辛かったと思います。
大川橋蔵さんは、1983年9月頃から体調を崩し始め、入退院を繰り返しながらも「銭形平次」の撮影を続けていたことが、病状を悪化させる一因となってしまいました。
特筆すべきは、橋蔵さんが健康に気を配る生活を送っていたにもかかわらず、がんに侵されてしまった点です。
大酒を飲むこともなく、タバコも吸わず、食事にも気を配り、常に腹部に健康帯を巻いていたという徹底ぶりでした。
医師に対して「なぜこんな病気になるのでしょう」と悔しさをにじませていたという証言が残されています。
当時の医療技術では早期発見が難しく、また多忙な撮影スケジュールが適切な治療のタイミングを逃す要因になったとも考えられます。
興味深いことに、橋蔵さんは自身の死期を予見していたとされ、1984年12月4日に「あと3日の命」と語り、実際にその3日後の12月7日午前1時29分に55歳という若さで息を引き取りました。
現代では大腸がん検診の普及により、早期発見・治療が可能になっています。
また、抗がん剤治療や手術技術も飛躍的に進歩し、5年生存率も大きく向上しています。
大川橋蔵さんの死は、定期的な健康診断の重要性を私たちに教えてくれる貴重な教訓となっているのです。
大川橋蔵の葬儀は
大川橋蔵さんの告別式は、1984年12月27日に、東京青山斎場で盛大に行われました。
親族以外では、「銭形平次」でライバル、三ノ輪の万七親分を十数年演じた遠藤太津朗さん、平次の女房、お静役を演じた香山美子さん、映画で共演した美空ひばりさん、中村錦之助さん、歌舞伎界からは、尾上菊五郎さんなどが出席されました。
弔辞は遠藤太津朗さん、香山美子さんなどが読まれたそうです。
特に香山美子さんにおいては、14年間、平次の女房役で共演して、本当の奥さんよりも一緒にいた時間が長かったと、橋蔵さんが生前おっしゃっていたそうです。
そのためか、香山さんは本当のご主人が亡くなったかのような悲しみようで、弔辞を読むときは、何度も言葉が詰まって出てこなかったといいます。
香山美子がお静をやってた、カラー時代の『銭形平次』が見たいんだけど、BSやCSでもあんまりやらないなあ。時代劇専門chで何本か見たけど。 pic.twitter.com/mnXlEvZ8AA
— 濱田研吾 (@hamabin1) June 18, 2024
妻の真理子さんが親族を代表としての挨拶で、「主人はたったひとつの宝はお前だと言ってくれました。日本一の主人でした」と述べたことは有名です。
夫は妻を宝と言い、妻は夫を日本一と言い、お互いの存在を唯一無二だということをおっしゃっていて、本当に素敵なご夫婦だと思います。
そして、大川橋蔵さんは、東京・雑司ヶ谷霊園にあるお墓に静かに眠っておられます。
大川橋蔵さんのお墓。
— はなっち!@ガハハな開発者 (@hjmkzk) December 21, 2024
確か歌手のイルカさんが幼少の頃ファンだったと記憶…@IRUKA_50th pic.twitter.com/zRJI9NHOLE
大川橋蔵の主な出演作品
大川橋蔵の若い頃の出演作品
大川橋蔵は1955年に東映に入社後、時代劇映画界で輝かしい功績を残しました。
デビュー作「笛吹若武者」(1955年、佐々木康監督)では美空ひばりや大友柳太郎と共演し、その端正な容姿と洗練された所作で一躍注目を集めることになります。
翌年には「若さま侍捕物帳」シリーズ(1956〜1962年、深田金之助ほか監督)の主演を務め、若き侍の品格と華やかさを見事に表現。
特に1959年に公開された「新吾十番勝負」(1959〜1960年、松田定次ほか監督)、その続編となる「新吾二十番勝負」(1961〜1963年、松田定次監督)は、歌舞伎で培った美しい立ち回りと繊細な演技が高く評価され、大川橋蔵の代表作として語り継がれています。
これらの映画作品の相手役には、東映の三人娘と言われた、お姫様女優の丘さとみさんや桜町弘子さんなどが演じました。
映画での演技は、六代目尾上菊五郎のもとで磨いた立女形としての経験が大きく活かされていました。足腰の強さと優美な所作を兼ね備えた立ち回りは、他の俳優の追随を許さないものでした。
本日12月7日は
— 東映チャンネル【公式】 (@toei_channel) December 6, 2023
俳優 #大川橋蔵 さんの命日です
東映チャンネルでは
大川橋蔵が紫右京之介を演じる映画を
本日放送!
▲12/7(水)あさ11時~
『#右京之介巡察記』
『#紫右京之介逆一文字斬り』
放送予定の出演作はこちら👇https://t.co/ysY6FtY1Nd pic.twitter.com/XWdMJzFCQ6
大川橋蔵の映画・テレビ・舞台の出演作品
大川橋蔵さんは、歌舞伎界と映像界の両方で輝かしい功績を残した稀有な存在でした。
1967年から歌舞伎座で開催された「大川橋蔵公演」は、毎年12月の恒例行事として定着し、「鏡獅子」「紅葉狩」「京鹿子娘道成寺」など、師である六代目菊五郎の当たり役に意欲的に挑戦し続けています。
舞台では、市川右太衛門との共演で「忠臣蔵」の浮舟太夫を演じ、菊五郎劇団で培った若女形としての実力を遺憾なく発揮しました。
テレビドラマでは、1966年から放送が開始された「銭形平次」で主演を務め、18年という長きにわたって時代劇の看板俳優として活躍することになります。
この作品は、フジテレビのチャンネル8で水曜日午後8時から放送され、888回という象徴的な回数で幕を閉じ、ギネス・ブックにテレビの1時間番組世界最長出演として認定されました。
舟木一夫が歌う印象的な主題歌とともに、颯爽とした平次の姿は多くの視聴者の心に刻まれています。
こちらの記事でも、「銭形平次」を紹介していますので、参考にしてください。
また、南座での定期公演も行うなど、東京と大阪を行き来しながら精力的に活動を続けた大川橋蔵さん。
歌舞伎で培った所作の美しさと、足腰の強さを活かした立ち回りは、やはり他の追随を許さない、唯一無二だったと評価されています。
テレビドラマでは、橋蔵さんは「銭形平次」終了後、「平岩弓枝ドラマシリーズ 蝶々さんと息子たち」(1984年5月~6月、フジテレビ系列)に、明日香流家元・清信役で出演します。
そしてこのドラマが、大川橋蔵さんの最後の出演となり、遺作となりました。
大川橋蔵の妻、息子、家系・家族について
大川橋蔵の家系について
大川橋蔵さんの家系・家族関係は、芸能界とも深いつながりを持ちながら、様々な絆で結ばれていました。
橋蔵さんは、生まれた実家から、幼い時に母方の祖母の家に養子に出され、次はそこから、歌舞伎界の大御所に気に入られ、1つ屋根の下で暮らすことで、その後大御所の妻の養子となって、大川橋蔵という名跡を継ぐこととなるという、ちょっと複雑な環境の中で育つことになりました。
では、以下で細かく解説していきます。
1929年4月9日、東京の柳橋で生まれた大川橋蔵は、目鼻立ちの整った美男子として知られていました。
母の笠原たかは柳橋の花柳界で育ち、父の田中進は人形町でガラス問屋を営んでいたことから、橋蔵は商家の次男坊として誕生したのです。
兄1人と妹2人の4人兄妹の中で育った橋蔵でしたが、生後間もなく母方の祖母・笠原よねの養子となりました。
笠原よねは、若かりし頃、柳橋の名妓として名を馳せた人物で、年を重ねた後も粋な気質と凛とした物腰を失わなかったといいます。
祖母は橋蔵を深く愛し、橋蔵も祖母を絶対的な存在として慕っていました。
祖母の夫である小野六三郎は芸名を市川瀧之丞という歌舞伎役者で、橋蔵は小野家の姓を継ぎ、小野富成として成長していきました。
小野家が芸能一家であったこともあり、1935年、大川橋蔵さんが6歳の時、市川男女丸の名で歌舞伎座の初舞台を飾り、歌舞伎の道へと進みます。
その後、1941年には六代目尾上菊五郎の妻の養子となり、丹羽姓を名乗ることになります。
1944年には二代目大川橋蔵を襲名します。
「大川橋蔵」は、三代目尾上菊五郎が、一旦引退してから、再び舞台復帰した時に名乗っていた、由緒ある名跡でした。
六代目尾上菊五郎には、養子の息子(七代目尾上梅幸)と実子の息子(二代目尾上九朗右衛門)がいましたが、妻の養子となり、大川橋蔵の名跡を継いだ橋蔵さんにも、「菊五郎」を継承する候補者としての資格が与えられ、3人の息子たちが切磋琢磨して芸を磨いたと言います。
六代目尾上菊五郎亡き後は、菊五郎劇団で修業を重ねていきました。
特に立女形として頭角を現し、七代目尾上梅幸や七代目中村福助に並ぶ存在として期待を集めたのです。
大川橋蔵さんは、名跡である「大川橋蔵」を継いだものの、六代目尾上菊五郎氏が亡くなったことで、強力な後ろ盾が無くなり、歌舞伎界での橋蔵さんの地位は微妙な立場になったことから、新たな映画界という新天地へ活躍の場を移すことになったのです。
妻は元祇園の芸妓、沢村真理子
大川橋蔵さんの妻は、元祇園の芸妓で沢村真理子さんと言います。(結婚後は丹羽真理子さん)
真理子さんは祇園でも最も売れっ子の芸妓さんで、大川橋蔵さんと大恋愛をして、芸能マスコミを賑わせました。
しかし、大川橋蔵さんは、女優の朝丘雪路さんともお付き合いしており、当時は込み入った関係となっていたそうです。
しかし、結果的には、橋蔵さんは朝丘雪路さんと別れて、1966年、37歳の時に、沢村真理子さんと結婚しています。
結婚当時、真理子さんは、すでに橋蔵さんの子供を妊娠していたという情報もあります。
息子は俳優の丹羽貞仁
大川橋蔵さんには、2人の息子さんがいます。
長男は丹羽朋廣(ともひろ)さん、二男は丹羽貞仁(さだひと)さんです。
長男、丹羽朋廣さんは、京都府出身、13歳ごろまで子役で活躍していました。
その後、青山学院大学に進学、大学を卒業後はフジテレビに入社、現在はプロデューサーの仕事をしているそうです。
二男、丹羽貞仁さんは、1969年5月3日生まれ、京都府出身です。
大川橋蔵さんが亡くなった後に、一家で東京に移住し、高校卒業後は明治大学に進学します。
明治大学に在学中の1988年、映画「ダウンタウンヒーローズ」(山田洋次監督)で学生役にてデビュー、大学を卒業後も俳優として活躍しています。
丹羽貞仁さんは、ドラマ「大岡越前」(TBS系列)、「渡る世間は鬼ばかり」(TBS系列)などに出演、テレビ以外でも、舞台 「乾いて候」(1989〜2000年、大阪新歌舞伎座等)(主演:田村正和)の天一坊役や、「明日の幸福」(原作・中野實、演出・石井ふく子)に寿雄役で出演するなどで活躍しています。
丹羽貞仁さんは、大川橋蔵さんの仕事仲間など、父親からのご縁でお仕事が決まることが多々あったそうです。
二世俳優であることに、「親の七光り」だとして、ネガティブな感情を持つ人もいる中で、丹羽さんの場合は、父親からのご縁を感謝して受け入れて、またそのことで新たなご縁に繋がるという、いい循環を作っていることが素晴らしいと思います。
これからもドラマに舞台にと、ご活躍を期待しています。
#毒薬と老嬢
— ❤カネル (@la___cannelle) April 21, 2022
生『長谷部先輩』感動した
渡鬼ファンです☺️
あの、橋蔵親分のご子息とは知りませんでした!😳#渡る世間は鬼ばかり#丹羽貞仁 さん pic.twitter.com/Aoo973aRSN
まとめ:大川橋蔵の死因は結腸がん、歌舞伎から映画、ドラマまで幅広く活躍した稀有な役者だった
これまでの内容をまとめますと、幼くして母方の祖母のもとへ養子に出された大川橋蔵さんは、歌舞伎界との縁を得ることになります。
1935年、わずか6歳で市川男女丸の芸名で初舞台を踏み、その後1941年には六代目菊五郎の養子となって、1944年に大川橋蔵を襲名しました。
若手歌舞伎では立女形として頭角を現し、七代目尾上梅幸、七代目中村福助に続く存在として期待を集めました。
特筆すべきは、歌舞伎界で培った所作の美しさと確かな演技力を、映画やテレビでも遺憾なく発揮したことです。
1955年に東映へ入社後は、「笛吹若武者」での銀幕デビューを皮切りに、「若さま侍捕物帖」や「新吾十番勝負」で主演を務め、時代劇映画の黄金期を支える大スターへと成長しました。
さらに1966年からは、テレビドラマ「銭形平次」で主演を務め、18年という長きにわたって視聴者を魅了し続けました。
この作品は、ギネス・ブックでテレビの1時間番組世界最長出演として認定される快挙を成し遂げています。
大川橋蔵さんの最期は、結腸がんとその肝臓への転移という過酷な病魔との闘いでした。
病に冒されてからも、彼は俳優としての責任感から休むことなく、テレビドラマ「銭形平次」の撮影や東京・大阪での舞台公演を精力的にこなしていました。
1983年9月頃から体調を崩し始め、入退院を繰り返しながらも第一線での活動を続けました。
そして、1984年12月7日午前1時29分、わずか55歳という若さでこの世を去りました。
大川橋蔵さんは、日本の芸能界を代表する名優として、歌舞伎から映画、テレビまで幅広い分野で活躍した稀有な存在です。
最期まで役者としての矜持を持ち続け、舞台に立ち続けた彼の生き様は、多くの後進たちの模範となっています。
大川橋蔵さんが出演している作品を観るなら、スカパー!やU-NEXTをおすすめします。
ドラマや映画が毎月定額で見放題のサービスですので、ぜひチェックしてみてください。
スカパー!