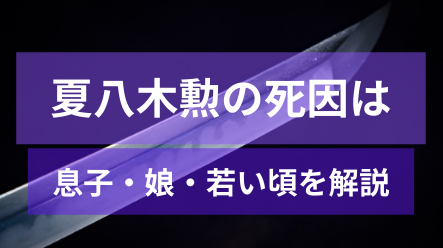昭和の刑事ドラマ歴代ランキング、懐かしの刑事ドラマ、歴代俳優、テーマ曲を解説
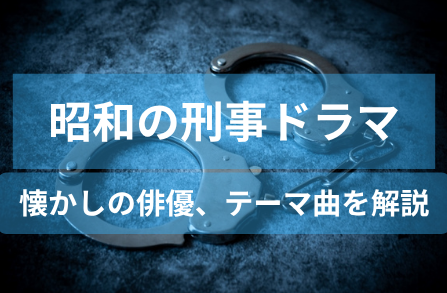
もくじ
昭和の刑事ドラマの魅力
昭和の刑事ドラマには、現代の作品にはない独特の魅力があります。
当時の作品は、単なる事件解決だけでなく、人間ドラマとしての深みと温かさを兼ね備えていました。
昭和の刑事ドラマが愛される理由
昭和の刑事ドラマが現在でも多くの人々に愛され続けているのは、その独特な魅力と時代背景にあります。
1970年代から1980年代にかけて制作された作品群は、現代の洗練されたドラマとは異なる温かみと人間味を持っていました。
当時の刑事ドラマは社会問題を積極的に取り入れ、視聴者に考えさせる要素を含んでいたのが特徴的です。
単純な勧善懲悪ではなく、犯罪者の心理や社会的背景まで丁寧に描写することで、深みのあるストーリーを展開していました。
また、登場人物たちの人間関係も現代ドラマより濃密で、仲間同士の絆や家族愛が色濃く描かれていました。
技術的な制約があった時代だからこそ、脚本や演技力で勝負する必要があり、それが結果として質の高い作品を生み出していたのです。
さらに、当時の俳優陣の個性的な魅力や、印象的なテーマ曲なども相まって、視聴者の心に強く残る作品となりました。
現代人が昭和の刑事ドラマに懐かしさと新鮮さを同時に感じるのは、こうした時代特有の魅力があるからなのです。
当時の社会背景とドラマの関係
1970年代から1980年代にかけて、日本社会は激動の時代を迎えていました。
沖縄返還、成田空港建設反対闘争、ロッキード事件といった重大な社会問題が相次いで発生し、国民の間には既存の権威に対する不信感が高まっていたのです。
こうした時代背景の中で生まれた刑事ドラマは、単なる娯楽作品を超えた社会派的な側面を持つようになりました。
また「Gメン’75」は、警察内部の腐敗という現実的な問題を出発点とし、組織の自浄作用への期待を込めた設定となっていました。
さらに「キイハンター」のような国際的なスパイアクションも、冷戦構造下での日本の立ち位置を反映した作品として捉えることができるでしょう。
これらのドラマは視聴者に娯楽を提供するだけでなく、複雑化する社会問題への関心を喚起し、正義とは何かを問いかける役割も果たしていました。
テレビというメディアが持つ影響力を活用し、社会への問題提起を行う姿勢は、現代のドラマ制作にも受け継がれている重要な要素といえます。
昭和の刑事ドラマランキング
ここでは、昭和の刑事ドラマをランキング形式で紹介していきます。
ランキングは、視聴率や放送期間、リアルタイムで視聴した時の当時の人気など、独断で決めさせていただきました。
第1位:太陽にほえろ
『太陽にほえろ』マカロニ&ジーパン編集オープニング pic.twitter.com/Y6OW5DKpAB
— ゴキブリシヌシヌ (@an_uehra) January 21, 2023
1972年から1986年まで約15年間にわたって放送された「太陽にほえろ!」は、日本のテレビドラマ史に燦然と輝く不朽の名作であり、刑事ドラマの金字塔といえます。(日本テレビ系列)
東京・新宿区にある警視庁七曲署の刑事たちが織りなす人間ドラマとアクションシーンの絶妙なバランスが、多くの視聴者を魅了し続けました。
この作品の最大の魅力は、個性豊かな刑事キャラクターたちにあります。
石原裕次郎演じるボス・藤堂俊介を筆頭に、マカロニ、ジーパン、テキサス、スコッチなど、愛称で呼ばれる若手刑事たちが次々と登場しました。
本作最大の特徴として、新人俳優の登竜門としての役割を果たしたことにあります。
新人俳優が若手刑事に扮して、その成長と活躍をドラマと現実が並行する形で展開されていきます。
この作品で、萩原健一(マカロニ刑事)、松田優作(ジーパン刑事)、勝野洋(テキサス刑事)、宮内淳(ボン刑事)、木之元亮(ロッキー刑事)、山下真司(スニーカー刑事)、渡辺徹(ラガー刑事)といった後のスターたちが、才能を開花させていきます。
彼らが成長し、やがて殉職という形で番組を去るパターンは、視聴者に深い感動を与え続けました。
この新人刑事が加入して活躍するパターンがウケて、放送開始当初の視聴率は、16〜18%だったものが、2代目新人刑事「ジーパン刑事」(演:松田優作)の登場後は20%以上をキープし、やがて30%以上をキープする大人気ドラマになっていきました。
また、犯人を追う際の迫力ある追走シーンも特徴的で、「走る刑事ドラマ」として親しまれています。
群像劇としての完成度の高さと、人間ドラマの深さが融合した傑作として、現在でも多くのファンに愛され続けています。
また、大野克夫さんが作曲したオープニングテーマ「太陽にほえろ!のメインテーマ」は、今なお多くの人に愛され続けている名曲です。
大野克夫さんは、作曲・編曲家、音楽プロデューサーとして活躍しており、沢田研二の楽曲や、「傷だらけの天使」、「名探偵コナン」など多くのドラマ、映画、アニメなどの音楽を手掛けています。
この楽曲は現在でも多くの人に愛され続けており、この曲を演奏した「井上堯之バンド」は実力、人気ともに評価が高く、作曲者の大野克夫さんが当時所属していたバンドでもあります。
私は子供の頃に、毎週このドラマを観ていました。
特に忘れられないのは、松田優作さん扮するジーパン刑事の殉職シーンです。
犯人に撃たれて、体から大量に流れ出る血が、手にべったりついているのを見て「なんじゃこりゃー!」と叫ぶ姿が忘れられないです。
それから、特に人気があったのは、勝野洋さん演じる「テキサス刑事」です。(とにかくすごい人気でした。)
短髪で爽やかな印象、普段は優しいが、犯人に猛然と立ち向かい、犯人を投げ飛ばす強さが人気の理由だったと思います。
人気があったので、テキサス刑事はなかなか殉職しなかったのですが、遂に殉職するという放送回(第216話「テキサスは死なず!」)の視聴率は、なんと、42.5%という高視聴率でした。
第2位:Gメン’75
1975年から1982年まで7年間にわたって放送された「Gメン’75」は、TBS土曜夜9時枠のアクションドラマシリーズの代表作として多くの視聴者を魅了しました。
警視庁から独立した特別潜入捜査班が国内外の凶悪犯罪に立ち向かうハードボイルドな作風で、全355話という長期シリーズとなっています。
丹波哲郎さん演じる黒木警部を中心に、倉田保昭さんや、藤田美保子さん、夏木陽介さん、原田大二郎さんなど、個性的で豪華な俳優さんらが、犯罪者たちと死闘を繰り広げる、迫力のあるドラマでした。
アクションシーンでは、銃撃戦や格闘シーンが迫力満点に描かれ、特に倉庫や港湾地区での追跡劇は緊張感に満ちていました。
また、犯人を追い詰める際の心理戦も見どころの一つで、取調室での駆け引きは視聴者を画面に釘付けにしました。
感動的なエピソードとしては、チームワークを重視したGメンたちの結束力を描いたシーンが挙げられます。
仲間が危機に陥った際の助け合いや、事件解決後の安堵の表情は、人間ドラマとしての深みを感じさせました。
さらに、一般市民との交流を通じて正義感を貫く姿勢も印象深く、単なるアクションドラマを超えた社会派作品としての側面も持っていました。
これらの名シーンが「Gメン’75」を不朽の名作たらしめているのです。
「Gメン’75」の成功により、TBS土曜夜9時枠は「キイハンター」「アイフル大作戦」「バーディー大作戦」と続くアクションドラマの黄金時代を築きました。
このドラマの主題歌は、「Gメン75のテーマ」(作曲・編曲:菊池俊輔)は、オーケストラによる演奏の重厚なイメージの曲で、多くの人に印象に残っています。
また、エンディングテーマの「面影」(作詞: :佐藤純弥、作曲・編曲:菊池俊輔 、歌唱:しまざき由理 )は、約140枚を売り上げる大ヒットとなりました。
私はTBS土曜夜9時枠のドラマは、「キイハンター」の頃からずっと観ていました。
「Gメン75」は、特にシリアスにこだわった作風だったのか、出てくる犯罪者は、本当に怖い人ばかりで、番組を観た後は、一人でトイレに行けなくなるくらい、子供心に怖かったのを覚えています。
特に「望月源治」(演:蟹江敬三)という殺人鬼が出てくる話の時は、本当に怖かった記憶があります。
第3位:キイハンター
「キイハンター」(KEYHUNTER)(1968年〜1973年、TBS系列、制作:TBS,東映)は、 警察では解決できない国際的な組織が絡んだ事件などを解決する国際警察の活躍を描いたドラマです。
チームのメンバーは、元諜報部員のキャップ、黒木鉄也(演:丹波哲郎)、外国語が堪能で、フランスの情報局の元諜報部員の津川啓子(演:野際陽子)、元新聞記者で、極めて高い身体能力と推理力で危険な捜査を見事にこなす風間洋介(演:千葉真一)を中心に、島竜彦(演:谷隼人)、谷口ユミ(演:大川栄子)、吹雪一郎(演:川口浩)ら若手メンバーを加えた個性豊かなメンバーで難事件を解決していくという内容でした。
このドラマの見どころといえば、千葉真一さんの命がけのアクションシーンでしょう。
ロープウェイでの宙吊りや、走る列車上での格闘シーンは、現在でも語り継がれる伝説的なアクションとなっています。
「キイハンター」は、海外でも放送されていて、千葉真一さんのアクションを見たブルース・リー(「燃えよ!ドラゴン」など有名)から共演の申し出があったり(実現はしなかった)、 ジャッキー・チェンは、千葉真一さんに憧れてアクションスターになったなど、影響を与えていました。
作品のもう一つの魅力は「なんでもアリ」の変幻自在な世界観です。
基本のスパイアクションから西部劇、任侠映画パロディ、コメディまで幅広いジャンルを取り入れ、毎回視聴者を飽きさせない工夫が凝らされていました。
レギュラー全員が毎回登場するのではなく、エピソードごとに異なるメンバーが活躍する構成も斬新で、「今週は誰が主役なのか」という期待感も作品の大きな魅力でした。
この多様性こそが「キイハンター」を単なるアクションドラマを超えた名作たらしめている要因といえるでしょう。
「キイハンター」の視聴率は、平均で30%を超えていたと言われており、大人気のドラマでした。
私は放送当時幼かったのですが、土曜日の夜9時からは、アクションシーンに手に汗握りながら、家族みんなでテレビを観たことを鮮明に覚えています。
毎回のように、千葉真一さんが宙吊りになったりして、危ない目に遭いながら何とか危機を脱するというのをハラハラしながら観ていました。
このドラマの主題歌である「非情のライセンス」(作詞:佐藤純弥、作曲:菊池俊輔)は野際陽子さんが歌っていたのですが、この曲を聴くと、今でも、あの頃のハラハラドキドキ感を思い出します。
第4位:西部警察
「西部警察」シリーズは、1979年から1984年まで5年間にわたってテレビ朝日系で放送された刑事ドラマです。
前作の「大都会」シリーズ(1976〜1979年、日本テレビ系列)を引き継いだ形のドラマでした。
警視庁西部警察署を舞台に、石原裕次郎さん演じる小暮謙三警視の指揮のもと、渡哲也さん演じる大門圭介部長刑事を筆頭とした特別機動捜査隊の活躍を描いた作品で、その圧倒的な迫力で視聴者を魅了しました。
西部警察シリーズの最大の魅力は、圧倒的なスケールで描かれる迫力満点のアクションシーンにあります。
大門軍団が繰り広げる銃撃戦や爆破シーンは、当時のテレビドラマの常識を覆すほどの豪華さでした。特に毎回登場する特殊車両「スーパーZ」をはじめとした改造車両群は、視聴者の度肝を抜く存在感を放っていました。
- 出演俳優…1万2,000人
- ロケ地…4,500箇所
- 封鎖した道路…40,500箇所
- 飛ばしたヘリコプター…600機
- 壊した車両の台数…約4,680台(1話平均・20台)
- 壊した家屋や建物…320軒
- 使用された火薬の量…4.8t などなど
上記は、ウィキペディアにあるデータの引用ですが、これらのデータを見ると、すごく手間暇とコストをかけた、スケールの大きい映画並みのドラマ制作だったことがわかります。
番組の平均視聴率は14.5%とそれほど高くはなかったのですが、これらのデータを踏まえて、ドラマとしてのスケールの大きさが他と群を抜いていたところ、インパクトの大きさを考えて、第4位にランクインさせていただきました。
そして、シリーズを通じて一貫しているのは、正義感あふれる刑事たちの熱い友情と絆で、ここにこのドラマの魅力を感じていた人も多いでしょう。
大門圭介部長刑事を中心とした捜査員たちが見せる男の美学は、実際、多くの視聴者の心を掴みました。
また、毎回異なる豪華ゲスト陣も見どころの一つで、当時の人気俳優や女優が次々と登場し、物語に華を添えています。
さらに注目すべきは、ロケーション撮影の豪華さです。全国各地の観光地や名所を舞台にした撮影は、まるで旅番組のような美しい映像美を提供しました。
これらの要素が組み合わさることで、西部警察は単なる刑事ドラマを超えた総合エンターテイメント作品として確固たる地位を築いたのです。
音楽面でも「西部警察メインテーマⅠ」(作曲:宇都宮安重)、「西部警察メインテーマPART-Ⅱ」(作曲:羽田健太郎)」など、印象的なテーマ曲が作品の緊迫感を高め、総合的なエンターテインメント作品として多くのファンに愛され続けています。
私は今でも、「西部警察メインテーマⅠ」を聴くと、ド派手な戦闘シーン、カーチェイスシーンなどが思い浮かび、どこかスカッとする感覚が沸き起こって、ワクワクが止まらなくなります。
これから気合い入れて取り組むぞ!という時には、私の頭の中には、「西部警察メインテーマⅠ」が流れています。
第5位:あぶない刑事
「あぶない刑事」シリーズは1986年に放送開始(日本テレビ系列)され、従来の刑事ドラマとは一線を画す革新的な作品として注目を集めました。
主演の舘ひろしと柴田恭兵が演じるタカとユージの名コンビは、型破りな捜査手法と軽妙な掛け合いで多くのファンを魅了しています。
最大の特徴は、シリアスな事件捜査の中にコメディ要素を巧みに織り交ぜた絶妙なバランス感覚です。
二人の刑事は時として規則を破り、上司に叱られながらも独自の方法で事件を解決していきます。
この型破りなアプローチは、当時の硬派な刑事ドラマの常識を覆す画期的なものでした。
また、横浜を舞台とした洗練された映像美も見どころの一つです。
港町の美しい景色をバックに展開されるアクションシーンは、都市的でスタイリッシュな印象を与えています。
刑事ドラマならではの、アクションシーン、カーチェイスや銃撃戦などの見応えのあるシーンでは、スローモーションや多角度からのカメラワークを駆使し、まるでハリウッド映画のような迫力ある映像を実現しました。
特に爆発シーンの演出は圧巻で、派手な特殊効果が話題となり視聴者を魅了したのです。
さらに、劇中で使用される音楽も印象的で、従来の刑事ドラマで使われていた重厚なBGMではなく、ポップスやロック調の楽曲を多用することで軽快なテンポを演出しました。
特にオープニングテーマ、「あぶない刑事(She’s So Good)」(作曲:舘ひろし)は多くの人に愛され続けています。
エンディングテーマ「冷たい太陽」(作詞:舘ひろし・久邇洋資、作曲:舘ひろし)は、舘ひろしが歌唱し、こちらも人気の曲です。
シリーズを通じて描かれる友情と信頼関係も重要な要素であり、困難な状況でも互いを支え合う姿が視聴者の心を打ちました。
昭和61年にテレビドラマから始まったこの「あぶない刑事」シリーズは、スペシャルドラマや、映画作品として何回も制作されて、最新作は、劇場映画第8作目の「帰ってきた あぶない刑事」が、2024年5月に公開されています。
実に昭和、平成、令和と3つの時代を通して視聴者に愛され続けた、類まれな作品と言えるでしょう。
当時、テレビを観ていましたが、登場人物がみんなスタイリッシュで、程よいコミカルさと緊張感のバランスが良くて、観ていて気持ちが良かったです。
これまでの刑事ドラマにはない、明るくて軽いノリが若者には抜群の人気で、社会現象にもなりました。
舘ひろしと柴田恭兵は、とにかくかっこよくて、浅野温子や木の実ナナも綺麗でした。
ドラマ開始時は、バブル前夜、そしてドラマが人気を保ち続けるバブル最中など、その時々の日本の活気や若者の希望・明るさなどが作品の中に溢れ出ているところが私は好きでした。
第6位:特捜最前線
「特捜最前線」は、1977年から1987年まで10年間、全509話を数える、「太陽にほえろ」に次ぐ長寿番組でした。(テレビ朝日系列、制作:テレビ朝日・東映)
このドラマは、「特命捜査課」という、警視庁本部や所轄が手がけた解決済事件の再調査や通常捜査では手に負えない難事件の解決を目的として作られた、警視庁の独立したセクションでの、神代警視正を中心としたメンバーの活躍が描かれた作品です。
この刑事ドラマは、リアルな警察捜査の描写と社会問題への鋭い切り込みを特徴としており、単なる刑事ドラマの枠を超えた社会派ドラマとして高く評価されています。
当時多くの刑事ドラマがありましたが、演じられる刑事の姿が、実際の刑事さんに一番近い刑事ドラマとも言われていました。
神代恭介課長(演:二谷英明)を中心に、ヘリ捜査専門の桜井(演:藤岡弘)、落としの名人 船村(演:大滝秀治)、地方出身のバイタリティ男 高杉(演:西田敏行)など、メンバーそれぞれが得意分野を持ち、個性がはっきりしていたので、熱血の桜井刑事が好きという人や、落としの名人船村さんが渋くて味がある、または、温かくて人情のある叶刑事が良かったなど、それぞれの推しがいたのも、このドラマの特徴と言えるでしょう。
個人的には、落としの名人、船村刑事(演:大滝秀治)と、射撃が得意で温厚な橘刑事(演:本郷功次郎)が印象に残っています。
また、この個性的なメンバーの1人1人にスポットを当てて、その人が主人公となり、毎回違った主人公のストーリーが見られるのも、このドラマの見どころの1つでした。
この作品が他の刑事ドラマと一線を画すのは、当時の社会情勢を巧みに織り込んだストーリー展開です。
公害問題、企業犯罪、政治汚職など、現実社会で起きている問題を正面から取り上げ、視聴者に問題提起を行いました。
特に、権力者の腐敗を暴く回では、制作陣の社会への強いメッセージが込められています。
現代の刑事ドラマにも大きな影響を与えた社会派路線の先駆的作品として、今なお多くのファンに愛され続けている名作です。
このドラマの最高視聴率は、1984年1月18日放送の回で27.4%を記録、1983〜1984年辺りは、20%以上をキープする時期もあり、平日(水曜日)の午後10時台の放送番組としては、高い視聴率を上げていました。(途中から、木曜午後9時台の放送枠へ移動)
このドラマの主題歌(エンディングテーマ)は、「私だけの十字架」(作詞:尾中美千絵 、作曲:木下忠司、歌唱:ファウスト・チリアーノ(イタリアの歌手))で、哀愁に満ちた、もの哀しい感じの曲ですが、子供心にとても印象に残っていました。
この曲を聴くと、人生は哀しみと共に歩くことだと言われているようで、年齢を重ねると、そうかも知れないなと、自分を慰めながらしみじみ思うことがあります。
第7位:噂の刑事トミーとマツ
「噂の刑事トミーとマツ」は、1979年〜1982年にTBS系列で放送された刑事ドラマです。
普段は気が弱いが、いざというときに超人的な力を発揮する、トミーこと岡野富夫(演:国広富之)と、猪突猛進のマツこと松山進(演:松崎しげる)との凸凹コンビが様々な事件を解決していくという刑事ドラマでした。
それまでのシリアスな刑事ドラマとは違い、アメリカンテイストのコメディタッチのドラマで、アクションシーンもあり、お笑いあり、人間ドラマありの日本では珍しい作品でした。
国内の刑事ドラマにおいては「バディもの刑事ドラマ」の元祖とされていて、「和製スタスキー&ハッチ」とも言われていました
(「スタスキー&ハッチ」とは、アメリカのドラマ「刑事スタスキー&ハッチ」のことで、1975〜1979年に放映された人気のドラマでした。
日本でも1977〜1981年に放送されていました。)
特に、マツがトミーに、「お前なんか男じゃない、おとこおんなで十分だ! おとこおんなのトミコ」と怒鳴りつけると、トミーにいきなりスイッチが入って、(耳がピクピク動く)超人的なパワーを発揮して犯人たちをやっつけるというパターンがお茶の間に受けていました。
(昭和という時代のため、現代では不適切とされる放送禁止用語も含まれています。)
コミカルで漫画っぽいところが刑事ドラマでは珍しく、子どもたちに大人気でしたね。
このドラマは大人気で、第1シリーズが65話、第2シリーズは41話、合計106話となるロングランのドラマで、第1シリーズの平均視聴率は17%を記録しています。
番組のオープニング曲「インストルメンタル」は、躍動感のある明るい雰囲気があり、エンディング曲の「WONDERFUL MOMENT」(作詞:三浦徳子、作曲:佐瀬寿一)は松崎しげるさんが歌うしっとりしたバラードで、雰囲気のあるいい曲でした。
ちなみに、私が住んでいた田舎では、民放のチャンネル数が少なく、このドラマは放送していなかったので、リアルタイムでは観ておらず、実際に観たのは、再放送やYouTubeなどでした。
しかし、少年少女向けの雑誌や新聞、テレビなどで、「噂の刑事トミーとマツ」が人気ドラマとして、度々取り上げられていたので、知っていました。
大人になってから観てもお笑いあり、アクションありと面白かったので、子供時代にリアルタイムで観ていたら、夢中になっていたかも知れないなーと思いました。
個人的には、「八重歯が可愛い」と言われ、アイドル的な存在だった国広富之さんが刑事役をやることが意外でしたし、「愛のメモリー」など、歌手として有名で演技経験のない松崎しげるさんが、いきなり主役をやっているのも、びっくりしました。
しかし、この通常では考えられない配役や、脇役に、石立鉄男さんや志穂美悦子さん、林隆三さん、石井めぐみさんなど、豪華俳優陣を迎えて、コメディタッチの刑事ドラマという今までにない新境地を開いて、それが大当たりしたドラマだったと思います。
現代では「相棒」など、刑事バディものは当たり前ですが、その元祖と言える作品がこの「噂の刑事トミーとマツ」だったと言われています。
主役をを演じた、国広富之さんと松崎しげるさんは、ドラマ内で、良いコンビネーションを見せてくれていますが、プライベートでも、国広さんが松崎さんの自宅に頻繁に遊びに行ったりなど親しくされていたそうで、公私ともに仲が良く、そのことが作品において、絶妙なコンビネーションを表現することに成功していたといえます。
第8位:熱中時代・刑事編
「熱中時代・刑事編」(1979年、日本テレビ系列)は、「熱中時代・教師編」で人気だった水谷豊さん主演の刑事ドラマです。
現代では、ドラマ「相棒」の杉下右京役で、刑事役の代表のような水谷豊さんですが、昭和時代、1970年代などは、「太陽にほえろ」の第1回の犯人役、映画「青春の殺人者」での殺人犯役など、どちらかといえば、捕まえる方より捕まる方の立場の役柄が多かったので、刑事役を演じるのは珍しかったです。
当時、水谷豊さんといえば、「熱中時代・教師編」が大人気だったのですが、私はむしろ、こちらの「熱中時代・刑事編」の方が好きでした。
このドラマの視聴率はかなり高く、平均視聴率は24.2%、最高視聴率は32.2%と、数字で見れば、「太陽にほえろ」に次ぐ、2番目の高視聴率で、大人気の刑事ドラマだったといえます。
水谷豊さんが歌った主題歌「カリフォルニア・コネクション」(作詞:阿木燿子、作曲:平尾昌晃)は、「ベストテン」(TBS系列)で4週連続1位、65万枚を売り上げて大ヒットしました。
それまでの刑事ドラマにはない、おしゃれで軽い感じと、主人公の早野武が、事件で出会ったアメリカの女性、ミッキーと恋愛、結婚するという、女の子が憧れるシチュエーションが描かれていて、私は子供の時に、毎週欠かさずに観ていました。
クラスの友人が水谷豊さんのファンで、このドラマのオープニングの水谷さんのモノマネをして、クラスのみんなを笑わせていたのが想い出に残っています。
ちなみに水谷豊さんは、このドラマで共演したミッキー・マッケンジーさんと1982年に国際結婚されています。
その結婚生活は短く、約4年で破局しましたが、その後、水谷さんは女優の伊藤蘭さんと再婚されました。
第9位:スケバン刑事
スケバン刑事シリーズは、和田慎二の漫画を原作として、1985年から1987年にかけて3作品が制作された学園アクションドラマです。(フジテレビ系列)
「スケバン刑事」は、従来の刑事ドラマの概念を根本から覆した革新的な作品で、主人公の麻宮サキが高校生でありながら刑事として活動するという斬新な設定は、当時の視聴者に強烈なインパクトを与えました。
第1作では斉藤由貴さんが麻宮サキ役を演じ、ヨーヨーを武器とした独特なアクションスタイルで話題となりました。
続く第2作「少女鉄仮面伝説」では南野陽子さんが主演し、より洗練されたアクションシーンと学園ドラマの要素を融合させています。
第3作「少女忍法帖伝奇」では浅香唯さん、大西結花さん、中村由真さんの3人が主演を務め、チームワークを重視した構成が特徴的でした。
シリーズ全体を通じて、不良少女が警察の秘密捜査官として活動するという設定が斬新で、従来の刑事ドラマとは一線を画した作品となっています。
また、各作品とも主演女優のアイドル性を活かしながら、社会問題を扱ったシリアスなストーリーも展開されました。
東映制作による本格的なアクションシーンと、青春ドラマの要素が絶妙にバランスされており、1980年代のテレビドラマ界に大きな影響を与えた記念すべき作品群です。
少年少女を中心に人気があり、第1作の平均視聴率は約13%でしたが、第2作は平均視聴率約14%、第3作は平均視聴率約14%、最高視聴率21.3%を記録して、当時のフジテレビのドラマ部門8位となるほどの人気ぶりでした。
番組の主題歌は、一連のシリーズで、共に主演のアイドルが歌唱しています。
第1作が「白い炎」(作詞:森雪之丞、作曲:玉置浩二、歌唱:斉藤由貴)
第2作が「悲しみのモニュメント」(作詞:来生えつこ、作曲:鈴木キサブロー、歌唱:南野陽子)他、
第3作が「STAR」(作詞:有川正沙子、作曲:タケカワユキヒデ、歌唱:浅香唯)他
どの主題歌もドラマの人気と相まって、オリコンチャート10位以内に入るなどヒットしました。
私は、和田慎二先生の漫画のファンだったので、「スケバン刑事」の実写版がどんな感じなのかなと思って観ていました。
トップアイドルが主人公を演じていたので、ちょっとイメージと違うかなと思いつつ、華やかでいいかなと思いました。
(個人的には、和田先生の「超少女明日香」シリーズを実写化して欲しかったです。)
特に第3作は、3人のチームワークや絆の強いところなど、観ていて頼もしくて女子の友情もいいなあと思って観ていました。
第10位:俺たちの勲章
『俺たちの勲章』1975年・日本テレビ / 東宝。全19話。
— カントク (@kantokuflash) September 24, 2024
松田優作と中村雅俊が演じた刑事ドラマ。
松田優作は「太陽にほえろ!」で演じたジーパン刑事とはまた違うストイックな刑事像を演じた。
中村雅俊も「われら!青春」のイメージを残しつつも新たな刑事像を演じている。… pic.twitter.com/55PlaUGOVe
「俺たちの勲章」は、1975年に日本テレビ系列(東宝製作)で放送された青春刑事ドラマです。
当時の若手実力俳優の2トップと言える「松田優作」と「中村雅俊」(共に「劇団文学座」に所属)が共演した夢のようなドラマでしたね。
ドラマの内容は、横浜にある「相模警察」本部の捜査一係に所属する中野祐二(松田優作)、五十嵐貴久(中村雅俊)という全く性格の違う2人の若手刑事の活躍を中心に描いた刑事ドラマで、刑事コンビものの先駆け的作品と言われています。
主人公の2人は、職場では厄介者として扱われていて、周囲から浮いた存在であるという設定も、仲間意識などを重んじた当時の刑事ドラマでは、珍しかったです。
このドラマの視聴率は、それほど良くなったそうですが、ドラマ自体の評価は高かったそうです。
刑事ドラマだったのですが、他の刑事ドラマとは一味違うなーと思っていたところ、後にこのドラマのプロデューサーである岡田晋吉氏が「青春ドラマとして制作していた」とインタビューに答えていたのを知って、納得がいきました。
また、毎回、注目されている若手女優さんが、ゲスト出演するのも楽しみの1つでしたね。
主演した中村雅俊さんの奥さんである、女優の五十嵐淳子さんもゲスト出演した1人です。
お二人はこのドラマでの共演がきっかけで、結婚したそうです。
実は、松田優作さんも五十嵐淳子さんを口説いていて、中村さんと競い合っていたという話は、芸能関係者の間では有名なことだそうです。
この番組は、プロ野球のナイターが中止の時などに放送されていたので、いつ放送されるかの見通しが立たず、毎週確実には観れないというマイナス面がありました。
そうなると、だんだん観るのを止めてしまう人もいますね。
私もその一人で、途中まで、楽しみに観ていたのですが、観たい時に観れないと、だんだんつまらなくなって、観るのを止めてしまいました。
今の令和の時代では、プロ野球は、ほとんどが全天候型のドーム球場で行われるので、ナイターの放送が中止になることはないでしょうが、
昭和の時代は、ほとんどの球場が、屋外の普通のグラウンドだったので、こんなこともあったなーと懐かしく思い出します。
「俺たちの勲章」のテーマ曲は、「俺たちの勲章 あゝ青春」(オープニング)、「追撃のテーマ」、「尾行のテーマ」など、作曲はすべて、当時若者のカリスマだった吉田拓郎氏(編曲はすべて、チト河内氏)が手掛けました。
「俺たちの勲章」のサウンドトラック版(演奏:トランザム)はオリコンチャート14位に入るなどヒットしました。
昭和の刑事ドラマの主な俳優
ここでは、昭和の刑事ドラマで活躍した主な俳優を解説していきます。
石原裕次郎
おはようございます٩(^‿^)۶
— 🌸生の松原🇯🇵🌸⛩️ (@1y8Hao8uLAOhRlF) July 16, 2025
1987(昭和62年〉7月17日、昭和の大スター 石原裕次郎の忌日。
数々の映画に出演、歌手としても多くのヒット曲を歌唱。
石原プロモーションを設立し、「西部警察」や「太陽にほえろ」等の人気ドラマを制作、多くの人気スターを輩出しました。
本日もよろしくお願いします pic.twitter.com/C6ucf1CLwu
石原裕次郎さん(1934年〜1987年、兵庫県出身)は、俳優、歌手、実業家で、日本の映画界において、戦後の日本映画を象徴する「昭和の大スター」として語り継がれる俳優です。
兄である石原慎太郎氏の芥川賞受賞作「太陽の季節」の映画化でデビューし、「狂った果実」で主演を務めました。
これらを通じて、戦後の若者の解放感や享楽的な生き方を描いた「太陽族」のブームを巻き起こし、その中心人物となりました。
そして、日活アクション映画の隆盛: 「嵐を呼ぶ男」「錆びたナイフ」「夜霧よ今夜も有難う」など、数多くのヒット作で主演を務め、日活を代表するスターとして黄金期を築きました。
俳優業だけでなく、歌手としても「嵐を呼ぶ男」「赤いハンカチ」「銀座の恋の物語」「ブランデーグラス」など、多くのヒット曲をリリースし、歌謡界にも大きな影響を与えました。
1963年には「石原プロモーション」を設立し、自ら映画製作にも乗り出し、第一回作品である「太平洋ひとりぼっち」は芸術祭賞を受賞し、その後も三船敏郎との共同制作である「黒部の太陽」など、スケールの大きな作品を手掛け、日本映画史に残る興行記録を打ち立てました。
映画産業が斜陽期を迎えると、活躍の場をテレビにも広げていき、「太陽にほえろ!」「大都会」シリーズ、「西部警察」シリーズでは、若手刑事たちを率いる「ボス」役として、幅広い世代から絶大な支持を得ました。
石原裕次郎さんは、単に刑事ドラマで活躍した俳優というだけではなく、映画俳優として、映画製作の独立やテレビドラマでの成功など、常に新しい挑戦を続け、日本のエンターテインメント界に多大な足跡を残した、まさに「伝説」と呼ぶにふさわしい人物です。彼の残した作品や生き方は、今もなお多くの人々に愛され続けています。
柴田恭兵
柴田恭兵さんは「あぶない刑事」ではアドリブをよくされますが、他のドラマ、映画でもされますね。
— 神村淳一 (@JUNBOU9001) May 25, 2025
この「半落ち」では素が出ているような気がして何回観ても泣いてしまいます😢#半落ち#寺尾聰#柴田恭兵 pic.twitter.com/ziJGqvKSRK
柴田恭兵さん(1951年生まれ、静岡県出身)は、俳優・歌手です。
そのキャリアを通じて、特に「刑事ドラマ」というジャンルにおいて、日本を代表する俳優の一人として不動の地位を築き上げました。
彼の名が広く知られるきっかけとなったのは、1986年に放送が始まったテレビドラマ「あぶない刑事」シリーズです。
舘ひろしさん演じる鷹山敏樹(タカ)と、柴田恭兵さん演じる大下勇次(ユージ)の破天荒ながらもクールな刑事コンビは、多くの視聴者を魅了しました。
スタイリッシュなアクションシーン、小粋なジョーク、そして男の哀愁を漂わせる演技は、当時の刑事ドラマに新たな風を吹き込み、社会現象を巻き起こしました。
同シリーズはテレビドラマだけでなく、劇場版も多数制作され、現在に至るまで根強い人気を誇っています。
「あぶない刑事」シリーズ以外にも、柴田さんは数々の刑事ドラマで主演を務めています。
例えば、「はみだし刑事情熱系」(1996~2004年、テレビ朝日系列))では、熱血刑事・高見兵吾を演じ、ヒューマンかつアクション満載のストーリーで好評を博し、シリーズ化されました。
また、それ以前にも、1978年の「大追跡」(日本テレビ系列)で連続テレビドラマに初レギュラー出演するなど、デビュー初期から刑事役を多く演じています。
柴田恭兵さんの刑事役は、単なる正義の味方にとどまらず、軽妙さとシリアスさを兼ね備えた深みのあるキャラクターとして描かれることが多く、その唯一無二の存在感は多くのファンに愛され続けています。
私は、柴田恭兵さんが、テレビ出演するなどメジャーになる前の、ミュージカル劇団、東京キッドブラザーズに所属していた頃から、注目していました。
当時は、これほどの名優になるとは思っていなかったのですが、情熱的というか、勢いのあるところがいいなと思っていました。
舘ひろし
舘ひろしさんは、(1950年生まれ、愛知県出身)俳優・シンガーソングライターです。
そのキャリアの中でも、特に「刑事ドラマ」における活躍は目覚ましく、多くの代表作を持っています。
舘さんの刑事ドラマでの活躍を語る上で欠かせないのが、1979年に放送が始まった「西部警察」シリーズです。
この作品では、石原裕次郎さんや渡哲也さんといった石原プロモーションの俳優たちと共に、ド派手なアクションと迫力ある演技で視聴者を魅了しました。
舘さんは、バイクを乗りこなすクールな刑事役を演じ、そのスタイリッシュな姿は多くの人々に強い印象を与えました。
そして、1986年にスタートした「あぶない刑事」シリーズで、柴田恭兵さん演じる大下勇次(ユージ)とコンビを組む鷹山敏樹(タカ)役で大ブレイクを果たします。
このシリーズは、先にも述べましたが、それまでの刑事ドラマにはなかった軽妙なセリフ回し、ユーモア、そして都会的なファッションセンスが特徴で、舘さんのクールでダンディな魅力が存分に発揮されました。
他にも、石原プロモーション制作の「ゴリラ・警視庁捜査第8班」(1989〜1990年、テレビ朝日系列)や「代表取締役刑事」(1990〜1991年、テレビ朝日系列)、宅麻伸さんとW主演した「愛しの刑事」(1992〜1993年、テレビ朝日系列)など、数々の刑事ドラマで主演や主要な役どころを演じています。
舘ひろしさんは、単にアクションをこなすだけでなく、その独特の渋みとユーモアを兼ね備えた演技で、刑事ドラマというジャンルに多様な魅力を加えました。その存在感は、日本の刑事ドラマ史において非常に大きなものです。
丹波哲郎
#余りにも存在感の大きいキャラクター
— 光路郎 (@Koujirou_ar) May 20, 2025
キャラというか、丹波哲郎
演じた役全てに説得力ある pic.twitter.com/ZIBUvS9KM6
丹波哲郎さん(1922年〜2006年、東京都出身)は、日本の俳優、声優、作家、そして心霊研究家としても知られる多才な人物でした。
彼のキャリアは戦後に本格化し、1950年代から1960年代にかけては、アクション映画やギャング映画で存在感を発揮しました。
特に、深作欣二監督作品や、海外作品への出演も多く、国際的な知名度も高めました。
彼の代表作としては、映画「砂の器」(1974年)での刑事役や、ハリウッド映画「007は二度死ぬ」(1967年)でのタイガー田中役などが挙げられます。
テレビドラマでは、TBSテレビの土曜日午後9時の放送枠である、「キイハンター」から「Gメン’75」まで一貫してシリーズの顔として活躍し、日本のアクションドラマ界に大きな足跡を残しています。
俳優業の傍ら、丹波さんは心霊現象やUFOといったオカルト分野にも深い関心を示し、自ら心霊研究家として活動しました。
多くの心霊番組に出演し、その独特の視点と語り口で、視聴者に新たな視点を提供し、著書も多数執筆、彼の心霊に関する考え方を広く伝えました。
晩年まで精力的に活動を続け、その個性的なキャラクターは最後まで多くの人々に影響を与えました。
また、丹波さんは、セリフは全く覚えてこないで、現場に来てから初めて台本を開き、その場でセリフを覚えて演技ができたという、天才的な能力の持ち主だったというエピソードが残っています。
松田優作
今日(11月6日)は松田優作さんの御命日です。
— pea_ch_1234 (@peach12349) November 6, 2024
ご存命でしたら75歳。
素晴らしいご活躍をされていたでしょう。
太陽にほえろ!
53話「ジーパン刑事登場!」
掲載させていただきます。#太陽にほえろ#ジーパン刑事登場#松田優作 pic.twitter.com/YZdawbpVH0
松田優作さんは、(1949年〜1989年、山口県出身)その圧倒的な存在感と演技力で、日本の映画・ドラマ界に多大な影響を与えました。
特に「刑事」役は、彼のキャリアにおいて重要な位置を占めています。
松田さんが全国的な知名度を得るきっかけとなったのが、1973年から出演した刑事ドラマ「太陽にほえろ!」での「ジーパン刑事」こと柴田純役です。
殉職したマカロニ刑事(萩原健一さん)の後任として登場したジーパン刑事は、長身で空手の有段者という設定で、従来の刑事像とは一線を画すワイルドな魅力を放ちました。
その型破りな捜査スタイルと、最期の殉職シーンの「なんじゃこりゃぁ!」というセリフは、今も語り継がれる伝説的なシーンとして知られています。
「太陽にほえろ!」降板後も、松田さんは刑事ドラマへの出演を重ねます。
1975年には中村雅俊さんとW主演した「俺たちの勲章」で、再び刑事役を演じて、1977年の映画「人間の証明」(佐藤純彌監督)では、棟居刑事役を演じ、刑事としての冷静な洞察力と内面の葛藤を見事に表現しました。
刑事役以外では、私立探偵・工藤俊作を演じたドラマ「探偵物語」(1979年、日本テレビ系列)が彼の代表作として挙げられます。
ここでは元刑事が探偵となった設定で、ハードボイルドな雰囲気とコミカルな演技を融合させ、松田優作の多面的な魅力を引き出しました。
「探偵物語」の放送当時、主人公の工藤が乗っている愛車「ベスパ」(イタリア製のスクーター)が若者の間で流行しました。
先日、「探偵物語」の再放送(テレビ埼玉)を観ましたが、やはり面白いですね。
松田優作という存在の魅力、視聴者を惹きつけるその輝きを感じましたね。
松田優作さんの「刑事」役は、単に事件を解決するだけでなく、そのキャラクターの内面や人間性を深く掘り下げたものが多く、視聴者に強い印象を残しました。
渡哲也
#サングラスが似合う俳優選手権
— わむ (@ys3yRT3XhhgjOkC) June 23, 2023
西部警察の大門さんこと渡哲也さん。 pic.twitter.com/ZdEjzJKGWg
渡哲也さんは、(1941年〜2018年、島根県出身)石原裕次郎さんに続く石原プロモーションの顔として、数々の映画やテレビドラマで活躍しましたが、特に「刑事」役は彼のキャリアを象徴するものでした。
渡さんの刑事としての代表作といえば、やはり「西部警察」シリーズで、彼は大門圭介部長刑事役を演じ、「大門軍団」を率いるカリスマ的なリーダー像を確立しました。
サングラスをかけ、ショットガンを構える姿は、当時の刑事ドラマに新たなヒーロー像をもたらし、その迫力あるアクションシーンは多くの視聴者を熱狂させました。
爆破やカーチェイスなど、規格外のスケールで描かれる捜査シーンは、渡さんの刑事役の代名詞となりました。
また、「大都会」シリーズでも、黒岩頼介刑事として主役を務めました。
渡さんが演じる黒岩刑事は、寡黙ながらも捜査への熱い情熱を秘めたキャラクターで、その無頼な魅力は視聴者を惹きつけました。
その後も、舘ひろしさんと共演した「代表取締役刑事」(1990〜1991年、テレビ朝日系列)では、課長を務める人情味豊かな刑事役を演じるなど、様々な刑事像を演じ分けました。
彼の演じる刑事は、単なる正義感だけでなく、人間味や哀愁、そして時には荒々しさも兼ね備えており、その深みのある演技は多くのファンを魅了しました。
渡哲也さん、本当にかっこよかったですね。
刑事役も、その他の役を演じてもかっこよかったですね。
個人的には、ドラマ「浮浪雲」(はぐれぐも)(1978年、テレビ朝日系列)の雲役も好きでした。
渡哲也さんは、私の理想の男性像でした。
まとめ:昭和の刑事ドラマには魅力的な作品がいっぱいある
これまで昭和の刑事ドラマを10作品をランキング形式で紹介してきました。
この他にも、人気があり印象に残る刑事ドラマがいくつかありました。
せっかくなので、ここで紹介させていただくと、私が印象に残っているものとして、「はぐれ刑事純情派」があります。
「はぐれ刑事純情派」(1979〜2009年、テレビ朝日系列)は、藤田まことさんが演じる安浦刑事の温かな人柄が視聴者の心を掴んだ名作刑事ドラマでした。
派手なアクションシーンなどはありませんでしたが、安浦刑事の、容疑者や被害者に対する深い共感力、事件の背景にある人間関係や社会問題を丁寧に掘り下げ、時には涙を流しながら真相に迫る姿は多くの視聴者に感動を与えました。
特に家族の絆や夫婦愛をテーマにしたエピソードでは、安浦刑事自身の家庭生活(妻の連れ子で義理の娘たちとの絆がある)と重ね合わせることで物語に深みを与えていましたね。
藤田まことさんというと「必殺」シリーズが有名ですが、この「はぐれ刑事純情派」も藤田さんの代表作の1つです。
このほかにも、「夜明けの刑事」(1974〜1977年、TBS系列、主演:坂上二郎)など、印象に残る刑事ドラマが多々あります。
一口に刑事ドラマと言っても、シリアスで、本物の刑事さんに近いものや、コミカルで子供も楽しめるもの、軽妙でおしゃれなもの、ド派手なアクションシーンやカーチェイスを売りにしているもの、人情味のある人間ドラマ的なものなど、作品によって、いろいろなテイストが楽しめるのが、昭和の刑事ドラマです。
今は大御所と言われるような俳優さんの若き日の初々しい姿も見れたり、当時の世相や人々の生活、時代の雰囲気などを感じられるのも、昭和の刑事ドラマの面白さでもあります。
BS放送や動画配信サービスなどで見られる作品がありますので、一度は是非観てみてはいかがでしょうか。
スカパー!